


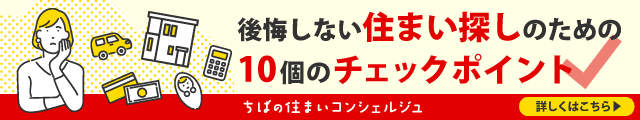
住宅購入では、色々な場面で税金がかかります。住宅購入に関して支払う税金・控除される税金について、概要や支払いの流れ、税額の算出方法などをまとめて解説していきます。

印紙税とは、不動産の売買契約書や建物の工事請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書などの契約書に対して課される税金です。
該当する契約書に収入印紙を貼り、割印を押すことで納税したとみなされます。
以下に、契約金額ごとの印紙税額をまとめました。
ここに挙げたのは一部のみですが、契約書の種類と金額によって税額が異なります。
| 記載された契約金額 | 不動産売買契約書 | 工事請負契約書 | 金銭消費貸借契約書 |
|---|---|---|---|
| 500万円超1千万円以下 | 5,000円※ | 5,000円※ | 10,000円 |
| 1千万円超5千万円以下 | 10,000円※ | 10,000円※ | 20,000円 |
| 5千万円超1億円以下 | 30,000円※ | 30,000円※ | 60,000円 |
(参考:国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで)
※「不動産売買契約書」と「工事請負契約書」の印紙税額は軽減税率適用後のもの。軽減税率は令和6年3月31日までに作成された契約書に適用されます。
なお、2022年5月から不動産取引における電子契約が解禁されました。電子契約だと契約書を紙で発行する必要がないため、印紙税が不要になるというメリットがあります。同様に、住宅ローンの金銭消費貸借契約においても電子契約を導入している金融機関が増えています。電子契約ができる場合は、できるだけ活用するといいでしょう。ただし、電子契約には電子契約手数料がかかる場合もあるため、あらかじめ確認しておきましょう。
登録免許税とは不動産を購入・建築した際、登記手続き時に納める税金です。取得した不動産の権利を明らかにするために所有権の移転登記や保存登記、また、住宅ローンを利用する場合は抵当権設定登記を行う必要があります。
通常、不動産取得時の登記手続きは司法書士に報酬を支払ったうえで依頼するケースが多く、必要書類の準備から登記申請、税金納付までの手続きをお願いすることができます。
税額は、原則として固定資産税評価額×税率で計算されます。
ただし、登記の対象となる不動産の種類(土地、建物)や登記の種類、取得の理由(売買、相続、贈与など)によって税率が異なります。
ここでは一般的な住宅購入(売買)時の税額を取り上げます。
| 不動産の種類 | 登記の種類 | 税額(原則) |
|---|---|---|
| 土地 | 所有権移転登記 | 固定資産税評価額×2.0% |
|
建物(新築) *注文住宅など |
所有権保存登記 | 固定資産税評価額×0.4% |
|
建物(新築) *建売住宅、マンションなど |
所有権移転登記 | 固定資産税評価額×2.0% |
| 建物(中古) | 所有権移転登記 | 固定資産税評価額×2.0% |
また、住宅ローンを借入する際に行う抵当権設定登記では、税額は債権金額(借入額)×0.4%で計算されます。
| 抵当権設定登記(住宅ローン) | 債権金額×0.4% |
計算方法からも分かるように、登録免許税は、購入する不動産の評価額が高いほど納付額も高くなります。
この負担を抑えるため、現在は「登録免許税の税率の軽減措置」がとられています。不動産や登記の種類にもよりますが、令和5年度の税制改正によって、最大で令和8年3月31日まで適用期限が延長されました。
(参考:国税庁 登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ)
| 不動産の種類 | 登記の種類 | 原則 | 軽減税率 | 適用期限 |
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 所有権移転登記 | 2.0% | 1.5% | 令和8年3月31日まで |
|
建物(新築) *注文住宅など |
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15%※ | 令和6年3月31日まで |
|
建物(新築) *建売住宅、マンションなど |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3%※ | 令和6年3月31日まで |
| 建物(中古) | 所有権移転登記 | 2.0% | 0.3%※ | 令和6年3月31日まで |
| 抵当権設定登記(住宅ローン) | 0.4% | 0.1%※ | 令和6年3月31日まで | |
ただし
※印のある項目では、軽減税率の適用を受けるには床面積が50㎡以上あることや、新築または取得後1年以内の登記であることなどの条件があり、注意が必要です。
また、新築の建物では、上記以外に特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅などの住宅性能が認められるとさらなる優遇を受けることができます。適用条件はもれなく確認しておくようにしましょう。
住宅購入時に支払う費用には、消費税がかかるものとかからないものがあります。
| 消費税がかかる |
|
|---|---|
| 消費税がかからない |
|
このなかで注意したいのは、建物です。
建物は、不動産業者等からの購入では消費税がかかりますが、個人の売主から購入する場合(中古物件など)にはかかりません。このように購入方法によって課税されるかどうかが変わるのです。
なお、不動産業者等から土地付きの戸建て(新築、中古問わず)を購入する場合は、土地価格には消費税はかかりませんが、建物価格には消費税がかかります。
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を取得した時にその不動産が所在する都道府県から課税される地方税です。
不動産を取得し、登記を行ってから6ヶ月程度で各都道府県から納税通知書が送られてきます。手元に届いたら支払期限までに金融機関等で支払いましょう。
税額は、固定資産税評価額×税率で計算されます。
ただし令和6年3月31日までに取得した土地・建物には以下の軽減税率が適用されます。
| 不動産の種類 | 税額(原則) | 軽減税率 |
|---|---|---|
| 土地 | 固定資産税評価額×4.0% | 3.0% |
| 建物(住宅) | 固定資産税評価額×4.0% | 3.0% |
これ以外にも、令和6年3月31日までに取得した土地・建物は、一定の要件を満たすと追加の軽減措置が受けられます。
新築住宅の場合、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば固定資産税評価額から1,200万円控除されます。さらにその建物が長期優良住宅に該当すれば、控除額が1,300万円に拡大されます。
中古住宅の場合は、床面積が50㎡以上240㎡以下でかつ居住用の住宅であること、新耐震基準に適合していることを満たせば、建物の新築年月日によって最大1,200万円が固定資産税評価額から控除されます。
また、土地については一律で固定資産税評価額が1/2になります。さらに、「土地の取得後3年以内に建物を新築」などの要件に当てはまれば、土地の税額から一定額が軽減されます。
軽減措置の詳しい内容は、各都道府県庁のホームページに掲載されていますので、住宅購入の際はしっかり確認しておきましょう。
千葉県 不動産取得税
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/shurui/fudousan.html
固定資産税と都市計画税は、住宅を購入して以降、毎年支払う税金です。
納付の時期が同じで内容も似ていることから、まとめて「固都税」などと呼ばれることもありますが、それぞれ別の税金です。
まず、固定資産税とは、土地・建物などの固定資産にかかる地方税です。
納税額は、固定資産税評価額×1.4%で計算されます。納付は一括または年4回の分割かを選択できますが、どちらの支払い方法でも納税額は同じです。
次に、都市計画税とは、都市計画事業などに充てるために市町村が課す地方税です。
納税額は、固定資産税評価額×制限税率(上限0.3%)で計算されます。上限0.3%となっている通り、自治体によって税率を変更できるため、地域によっては0.3%を下回るケースがあります。
なお、固定資産税と都市計画税には、土地や新築住宅に対する軽減措置がありますが、新築住宅に関する軽減措置は、「新築した時から一定期間のみ固定資産税が減額される」という期間限定のものです。この軽減措置の適用対象は令和6年3月31日までに建築が完了している建物である点も、あわせて留意しましょう。

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入したときに一定の要件を満たすと所得税や住民税が控除される制度です。
控除額は原則「年末時点のローン残高×0.7%」ですが、控除を受ける本人の所得税・住民税の金額によって変わってきます。また、控除される期間は原則13年ですが、物件の種類によっては10年になる場合もあります。
控除を受けるためには確定申告が必要です。会社員の場合は、初年度のみ確定申告すれば、2年目以降は年末調整で対応可能です。
なお住宅ローン控除は、住宅ローンを利用すれば誰でも受けられるというわけではありません。
住宅の種類やローン借入額、所得などの要件がありますので、利用したい場合は要件をしっかり確認するようにしましょう。
住宅ローン控除は、2024年から控除額が引き下げられることが決定しています。
控除率は0.7%のままで変わりませんが、新築・買取再販※の住宅は、長期優良住宅・低炭素住宅・省エネ住宅等にあたらない場合、ローン控除の対象外になってしまうほか、控除の対象となる借入額の上限も変更されるため注意が必要です。
※買取再販とは、不動産業者が中古物件を買い取り、リフォームやリノベーションして再度販売すること。
以下に変更点をまとめました。
| 新築・買取再販 | 入居年/ローン残高の上限 | 控除率 | 控除期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅の種類 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 0.7% | 13年 |
|
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
5,000万円 | 4,500万円 | |||
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 | |||
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | |||
| その他の住宅 | 3,000万円 | 対象外 | |||
| 中古 | 入居年/ローン残高の上限 | 控除率 | 控除期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅の種類 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 0.7% | 10年 |
|
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
3,000万円 | ||||
| ZEH水準省エネ住宅 | |||||
| 省エネ基準適合住宅 | |||||
| その他の住宅 | 2,000万円 | ||||
ただし、住宅ローン控除の控除額が引き下げられるからといって、焦って住宅購入を進めてしまうのはおすすめしません。今後のライフプランや資金計画をよく考えたうえで、ご自身やご家族にとってベストなタイミングで購入しましょう。
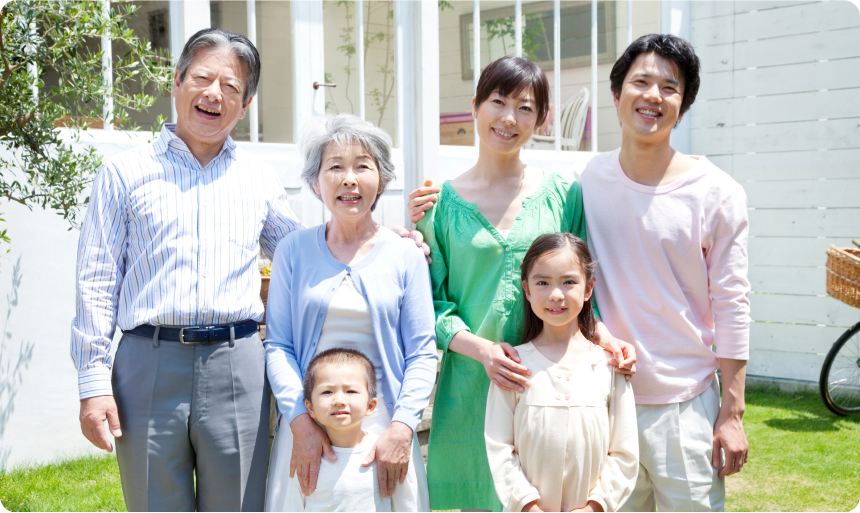
住宅取得等資金贈与とは、自分が住むための住宅を購入する際に両親や祖父母から資金援助をしてもらった場合、最大1,000万円まで非課税となる特例です。
贈与を受けた人が日本在住、贈与を受けた年の1月1日の年齢が18歳以上、贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下などの条件があります。
また、贈与された資金は住宅の取得に使わなければならない、という制限があります。そのため、諸費用の支払いやローン返済に充てることができない点には注意しましょう。
住宅取得等資金贈与の非課税制度は、2023年12月31日で終了となります。
住宅取得等資金贈与の非課税制度は、制度が始まった当初は最大で3,000万円が限度額となっていました。しかし年々縮小され、2023年末で終了となった経緯があります。
この背景を踏まえると、今後、制度が復活する可能性は低いのではないかと考えられます。
2024年以降に住宅取得資金を援助したい、または援助してもらいたいという場合は、事前に金額の相談を行い、暦年贈与等の通常の枠組みを利用して、計画的に取り組むことをおすすめします。
住宅購入にはさまざまな税金がかかる一方で、軽減措置や優遇制度が数多く用意されています。
これまで解説してきたように適用条件や対象期間などが細かく決まっており、内容が分かりにくいものも多いため、不明な点があれば税務署や税理士に相談し、あらかじめよく確認しておきましょう。
また、固定資産税等は住宅購入後、毎年かかってくる税金です。維持費として住宅ローンの返済とあわせて無理なく支払えるようにしっかりと資金計画することが大切です。
「ちばの住まいコンシェルジュ」では住宅ローンの相談はもちろん、マイホームの資金のアドバイスやライフプランシミュレーションの作成も行っています。
中立的な立場から一人ひとりに寄り添ったご提案をさせていただきますので、お気軽にご予約ください。


現在のご年収や、お借入希望額などから、
かんたんにシミュレーションできます!