
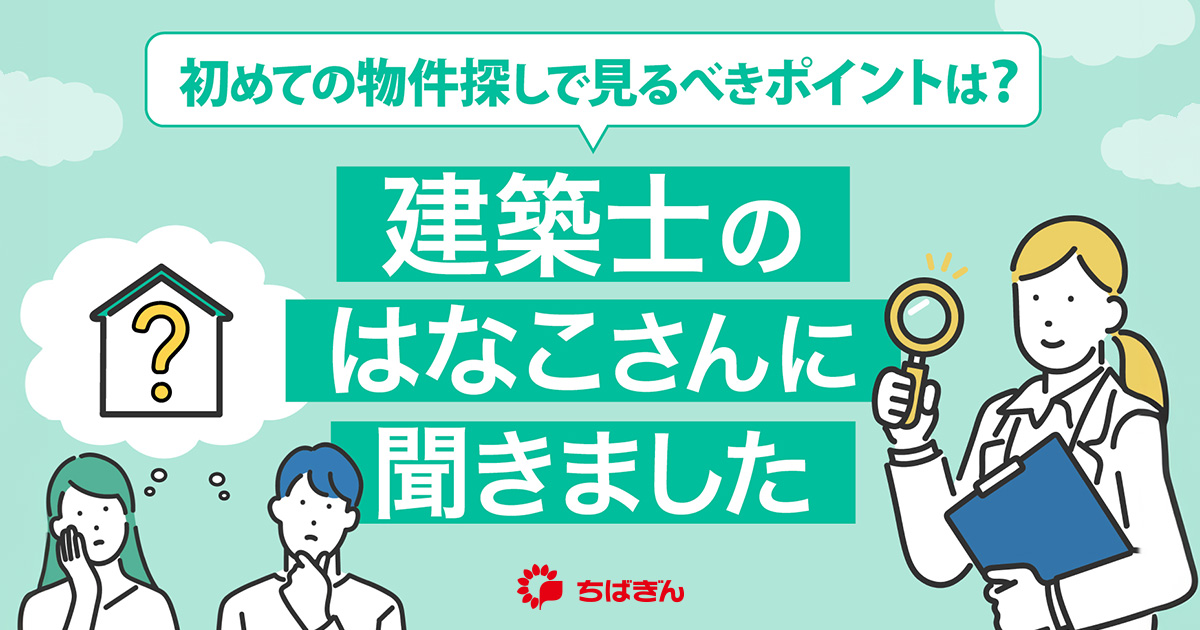

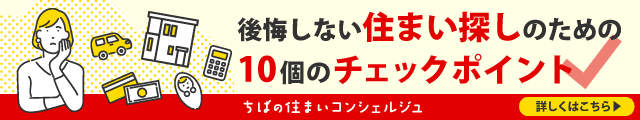
そろそろマイホームの購入を検討したいと考えていても、実際には何から始めたらいいのかわからない方が多いのではないでしょうか。戸建てとマンション、新築と中古のどちらがいいのか、エリアはどこがいいのかなど、悩むポイントはたくさんあります。
そこで、SNSなどでマイホームづくりや間取りのポイントを紹介している建築士のはなこさんに、物件やエリアを選ぶ際に見るべきポイントを教えていただきました。


——マイホームとひと口に言っても、戸建てかマンションか、新築か中古かなど、たくさんの選択肢があります。どのように絞り込んでいけば良いのでしょうか。

まずは、自分たちがどういう暮らしをしたいのか、家族で話し合ってみてください。
いろいろな条件を出したとしても、実際に条件に合う物件があるかはわからないので、あらかじめ家族で条件の優先順位をつけておく必要があります。大きな予算をかけて終の住処となる家を建てたいのか、それとも限られた予算で住み替えを前提とした家を持ちたいのか、それによっても選択肢は大きく変わってきます。
また、現実的な問題として、全体の予算感を把握する必要もありますよね。特に新築戸建ての場合は、土地から探さないといけないケースも多いです。
そうなると、土地と建物を合わせてどのくらいの予算をかけられるのか、ざっくりとでも把握しておくと良いですね。中古物件であれば、リノベーション費用まで含めて予算を考えましょう。

——ある程度方向性が決まったら、住宅エリアの選択も必要です。エリア選びのポイントを教えてください。

まずは、交通アクセスをチェックしましょう。都心エリアで徒歩や電車、バスでの移動がメインになるのであれば、駅やバス停までかかる時間と道のり、夜も安心して歩けるように街灯があるかなどを確認してください。郊外エリアで車移動がメインであれば、周辺の道路の混雑状況や幹線道路への出やすさなどがチェック項目ですね。
昼夜で街の雰囲気が変わる地域もあるので、時間帯を変えて現地に行ってみることも大切です。特に都心は、夜間の治安に対する不安や、交通量が多い時間帯には騒音が気になる場合もありますから。
あとは、ハザードマップで洪水や地震などの自然災害によるリスクについても調べておきたいですね。

また、将来的に売却を考えている場合は、坪単価が落ちにくい地域や中古物件が売れやすい地域を中心に見てはどうでしょうか。エリアごとに平均的な坪単価があって、近くに大規模な商業施設が建つとか、大きな道路が通るなどの特別な理由がない限り、急激には変動しないものなので、今の価格を基準に検討するのが良いと思います。
・交通アクセス
・時間帯による街の変化
・自然災害によるリスク
・平均的な坪単価
——注文住宅を検討する際、土地探しのポイントは何ですか?

建築士として一番気になるのは、その土地の用途地域(※1)です。用途地域によって建物の面積や容積率が決まってくるので、建てられるものに制限が出てくる場合があります。
土地の形状や地盤もチェックしますね。土地の中に高低差があると、深い基礎が必要になるなど、通常より基礎工事や擁壁工事に費用がかかることがあります。軟弱地盤だと、地盤改良費がプラス100〜200万円かかることも。土地の購入価格だけでなく、基礎工事や地盤改良にかかる費用も確認しておく必要があります。
また、分譲地として開発された土地の場合は問題ないのですが、もともとある土地、特に整備されていない土地だと、隣接地との境界が明確になっていないケースもあります。境界杭がしっかりと入っているか確認しましょう。水道やガスなどのインフラ設備の引き込み工事がなされているかどうかも確認してください。
※1 用途地域とは、住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、13種類あります。用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて建てられる建物の種類が決められます(出典:国土交通省「用途地域」)。
・用途地域の種類
・土地の形状と地盤の強度
・隣接地との境界
・インフラ設備の引き込み工事の状況
——注文住宅を選択した場合、建築会社を探す必要がありますよね。その際に気をつけるポイントはありますか?

建築会社を選ぶ際は「基本の性能や希望の間取りが実現できる金額感か」「施工力が高いか」という2点を重視しましょう。
住宅メーカーや設計事務所、地域の工務店などが選択肢としてあると思うのですが、それぞれで坪単価が決まっていることも多いです。気密性、断熱性、耐震性などの基本的な住宅性能を踏まえたうえで、予算内で希望する家が建てられるかを確認してください。ただし、建築会社によって住宅性能の基準や項目が違うので、見積もりを比較する際は、自分たちが求める性能や項目に統一して確認する必要があります。
希望の間取りを実現できるかという点については、契約前に大まかにでも間取りのイメージを持っておくと良いですね。契約後に間取りは変えられますが、実際には打ち合わせ時間が思ったより取れなくなってしまう場合もあるので。
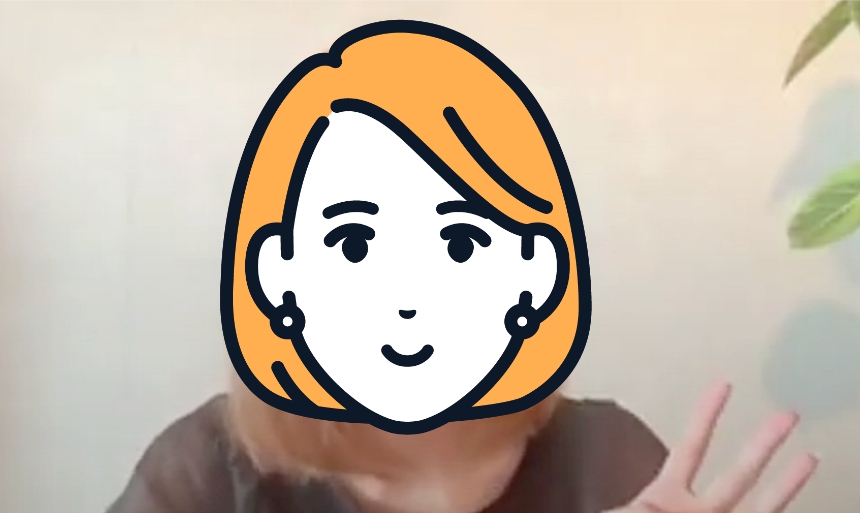
——具体的な間取りのイメージが湧きにくい方もいると思うのですが、どうやって組み立てていけば良いのでしょうか?

確かにゼロから考えるのは難しいので、そういう場合は今住んでいる家の間取りを参考にして、次はこうしたい、ここを直したいなど、変えたいポイントから考えてみてください。
あとは、いろいろな間取りを実際に見てみるとイメージが膨らむので、完成見学会に足を運んでみてはいかがでしょうか。モデルハウスと違って、実際に人が住む前の家を見学できるので、より実感が湧くと思います。それから、インスタグラムなどでいろいろな家の間取りを見て、素敵だなと思った要素を取り入れていくのもいいと思います。
——もう一つの「施工力が高い」とは、どういうことでしょうか

打ち合わせ自体はうまくいっても、工事の体制が整っていないと、打ち合わせの内容を実現できないこともあります。なので、施工力がとても大事になってくるんです。
住宅性能って、結局は工事のクオリティによって左右されますから。そういう意味で、最近はホームインスペクション(※2)という第三者チェックを導入される方も増えていますね。
※2 ホームインスペクション(住宅診断)とは、住宅に精通した専門家が、住宅の状況や施工の不具合などを第三者として調査するサービスのこと。
——その他に注意すべきポイントはありますか?

契約した建築会社によって、入れられる住宅設備が変わってくる場合があるので、どうしてもこだわりたい設備がある場合は、それを入れられるかどうか契約前に確認しておいたほうがいいと思います。
それから、意外に見落としがちなのが、完成までの時間です。同じ家を建てるにしても、建築会社によって工期は変わってきます。予約がいっぱいで着工まで時間がかかる場合や、すぐに着工できるけど工期が長くかかる場合もあり、引き渡しまでの期間はそれぞれ異なります。「子どもの入学前に引っ越したい」などの希望がある場合は、忘れずにチェックしてください。
・理想の住宅を叶えられる金額感か
・施工力
・希望する住宅設備を入れられるか
・引き渡しまでの期間

——先ほど間取りの話がありましたが、完成見学会などで新築戸建てを内見する場合にチェックすべきポイントを教えてください。

内見して、この部屋は開放感があるなとか、狭いなと思ったときに、部屋の広さの具体的な数値と自分が感じた広さの感覚をすり合わせてみてください。広さは体格によって感じ方がかなり違うので、求める広さを数値と体感の両方で把握しておくことが大切です。
あとは、家の中で気に入った要素をメモしておきましょう。実際に家を建てるときには、照明や壁紙、床の色まですべて決めなくてはいけないので、実物を見てイメージを固めておくといいと思います。
——では、中古の戸建物件を内見するときのポイントをお願いします。

中古物件の場合は、現状の把握が一番大切です。雨漏りなど、補修すべきポイントがないかチェックしてください。木造であれば、床下点検口からシロアリ被害がないか確認したり、天井点検口から天井裏の状態を見たりしましょう。過去の地震などの影響で家が傾いているケースもあるので、床が水平かどうかもチェックしたほうがいいですね。
——マンションを内見する際は、何を見たらいいでしょうか。

新築マンションは建つ前に予約購入する場合が多いので、内見とは違いますが、時間帯を変えて何度か完成予定地へ行って、治安や騒音をチェックする必要があると思います。共用スペースの利用規約も確認していただきたいですね。ゴミ出しの方法や組合役員の頻度などは、建物とは関係ないですが、住み心地という面では重要ですから。
——中古マンションの内見の場合はどうでしょう?

マンションのエントランスや共用部分が整った状態か、管理が行き届いているか、チェックしてください。中古物件の場合、照明が暗くなっているとか、ポストが壊れているとか、そういう不具合が放置されていたら、管理体制に不安があるかもしれません。
また、築10年以上だと音や振動が気になる場合もあるので、その点も確認しましょう。おすすめは、管理人さんと話してみること。どんな住人が多いかなど、管理人さんの声を聞くと住環境がある程度把握できますよ。
▼新築戸建ての場合
・求める広さを数値と体感の両方で把握
・照明や壁紙、床の色など
▼中古戸建ての場合
・雨漏りなど、補修すべきポイントがないか
・シロアリ被害の有無や床下、天井裏の状態
・床が水平かどうか
▼マンションの場合(新築・中古)
・周辺環境
・共用スペースの利用規約
・共用スペースの管理状況
・音や振動

——注文住宅やリノベーション物件の場合、予算と希望する条件の折り合いをつけるのが難しいこともあるかと思います。どうやって希望の優先順位を決めていけばいいのでしょうか。

家を建てるときや購入するとき、私は「自己理解」が一番大事だと思っています。自分が何に価値を感じるのか、そこを考えてほしいんです。その要望を取り入れたいのは、単にオシャレだからなのか、それとも生活が回りやすくなるからなのかなど、背景までしっかりと考えてもらえたらいいと思います。
——「自己理解」を深めるには、どうしたら良いのでしょうか。

具体的には、朝起きてから夜寝るまでの自分の行動パターンを思い返してみて、どういう動線と設備が必要なのか考えてみるといいと思います。あとは、自分が何を大切に思っているのか、自分の性格を振り返ってみるのもいいですね。
例えば、片付けが得意な人と苦手な人に同じ収納を用意しても、苦手な人はうまくいかない部分が出てくると思うんです。であれば、その人に合った収納を考えるべきです。そういう意味では、要望を出すというより、自分の性格や暮らし方を建築士に聞いてもらって、その解決策を提案してもらうのがいいと思います。建築士は家づくりのプロですから。

——はなこさんは、マイホーム購入の相談をたくさん受けていますよね。マイホーム購入がうまくいく人に共通する要素はありますか?

私の経験から言うと、「自己理解ができている人」「家族で話し合えている人」「情報を比較検討できる人」、あとは「プロに遠慮しない人」でしょうか。打ち合わせ中、建築士に気を遣って、間取りを変更したくても最後の最後まで伝えられない方もいらっしゃるんです。変更が遅くなるほど、引き渡し時期が延びてしまったり、変更できなくなってしまったりすることもあるので、やっぱり自分の思いをしっかりと伝えることが大事だなと思います。
情報の比較検討については、建築会社を選ぶ際にも1社をピックアップして内容を詰めていくのではなく、複数社を同時に比較して自分で決めることが大事です。そういう「自分で選んだ」という経験の積み重ねが、選択の自信につながると思うんです。
そのとき、選択の理由が自分の中で明確だと、より後悔が少ないと思いますね。マイホーム購入は、選択肢が無限大です。だからこそ、情報を早めにキャッチして比較検討し、一つ一つ選択していくことが、マイホーム購入成功への近道だと思います。
マイホーム購入は、エリア選び、土地選び、物件選び、建築会社選びなど、数えきれないほどの選択の連続。それらを後悔なく進めていくためには、情報をいち早くキャッチして、自分の生活や暮らしと照らし合わせながら、自分にとって何が必要なのか見極めていくことが大切です。記事で紹介したポイントを押さえながら、理想のマイホームを叶えましょう。
「ちばの住まいコンシェルジュ」では、複数回の面談を通して、情報提供や希望条件の整理、ライフプランシミュレーションを行っているほか、不動産会社・建築会社のご紹介もしています。後悔のない選択をするためにも、ぜひプロへの相談も検討してみてください。


現在のご年収や、お借入希望額などから、
かんたんにシミュレーションできます!