目次
閉じる
- 第1部
- 第2部
- 第3部

目次
閉じる
1873年に木更津県と印旛県が合併して千葉県は誕生した。近代以前の千葉では、大消費地である江戸の台所として農業と水産業が主な生業であった。水系に恵まれた江戸川・利根川流域では稲作が盛んであったのに対し、高低差のある下総台地では畑作が普及した。また、周囲には好漁場が多く、沿岸地域では干鰯や海苔など水産加工も行われた。
さらに、立地と気候風土に適した地場産業も各地に誕生し、水運の発達や街道の整備などに伴って発展を遂げていった。野田・銚子の醤油醸造業、流山のみりん醸造業、木更津の海運業、勝山(鋸南町)・和田浦(南房総市)の捕鯨業、嶺岡牧(南房総市・鴨川市の一部)の酪農業などが代表的である。

近代に入り、こうした地元の実業家や有力者のなかには金融業へと進出し、銀行設立の発起人となる者も現れた。
昭和初期に千葉県に本店を置く銀行は6行(千葉合同、小見川農商、第九十八、野田商誘、千葉貯蓄、東金)あったが、千葉銀行が創立をみる直前の1943年2月に、東金銀行は千葉合同銀行に営業を譲渡し、解散した。
千葉銀行は、1943年3月31日、千葉合同銀行、小見川農商銀行、第九十八銀行の3行が合併して誕生した。創立後の1944年3月に千葉貯蓄銀行を合併し、同年6月に野田商誘銀行の営業を譲り受けたことで、当行は県内に本店を置く唯一の銀行となった。
したがって、本節では合併3行と千葉貯蓄銀行、野田商誘銀行の略史を記述する。
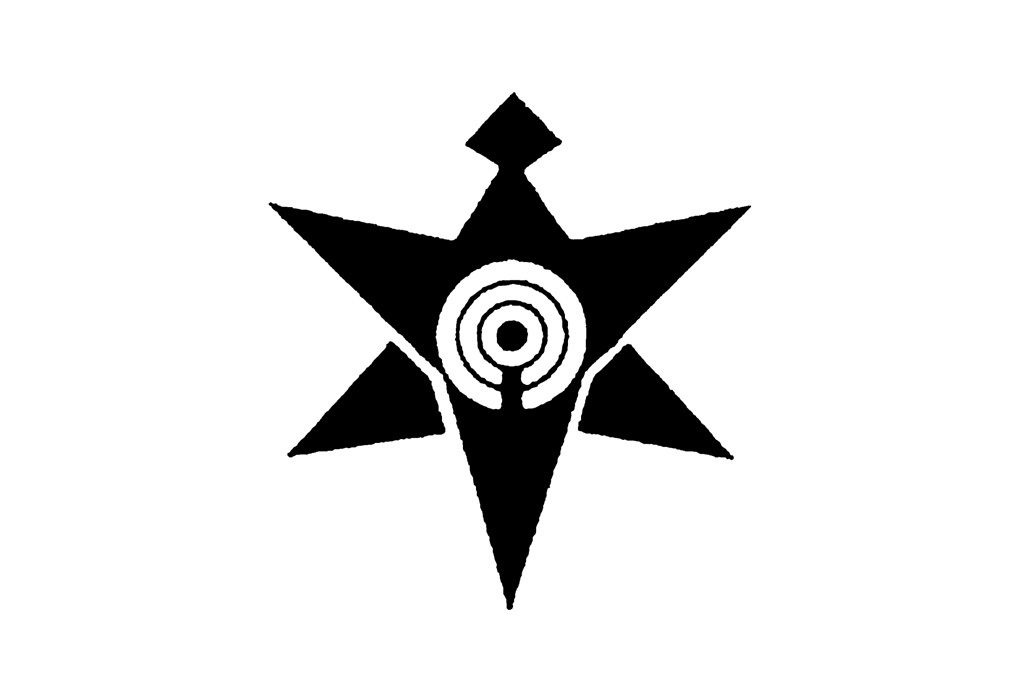
千葉合同銀行の歴史は、1896年2月に開業した成田銀行に始まる。資本金は20万円で、1900年までに本店のほか東京支店、佐原支店、四街道出張所を設けた。
開業当初、営業は順調であったが、1901年に起こった金融恐慌※7の影響が千葉県にも波及し、同年10月には成田銀行も休業に追い込まれた。取締役らが個人で借り受けた資金を融通するなどして、翌年2月に営業を再開したものの、業績は好転せず、1914年10月には店舗も本店のみとなった。
1914年、再び銀行取付けが全国に広まるなか、成田銀行も経営難に陥り、川崎銀行※8に援助を求めた。川崎銀行は明治初期から県下に数か所の支店を設け、当時、千葉県における都市銀行として大きな勢力を持っていた。

川崎銀行の後援を得た成田銀行は、その後、積極的に県内外の中小銀行を合併していった。1918年6月には東京に本店がある日出銀行を吸収し、営業範囲を上総・下総から武蔵(東京都・埼玉県)にまで広げた。このとき、行名を「総武銀行」と改め、同年11月には本店を千葉町(現・千葉市)に移転した。大正年間に総武銀行が吸収合併した銀行は、前述の日出銀行のほか、夷隅、鶴舞、北総(海上郡旭町、現・旭市)、多古、成東の5行で、資本金は野田商誘銀行の300万円に次ぐ202万円となった。

しかし、1923年の関東大震災は総武銀行の経営にも打撃となり、再び川崎銀行に救済を求めざるを得なくなった。のちに千葉銀行初代頭取になる古荘四郎彦は、1926年5月に川崎銀行から派遣され、専務取締役(川崎銀行千葉支店長・千葉県総支配人を兼務)として総武銀行の再建に努める一方、県下銀行の合同に力を注いでいった。
この時期、政府は地域内での地方銀行の合同を勧奨し、核となる銀行がなかった地域では川崎銀行が合同を促進した。1925年、川崎銀行は経営の行き詰まりから援助を求めてきた三協銀行(香取郡佐原町、現・香取市)、安房合同銀行を手中に収め、古荘をはじめとする役員を送った。川崎銀行には総武銀行を含む3行を県内銀行合同の中心に据える狙いがあり、県当局もこれを支援し、それまで千葉県農工銀行に取り扱わせてきた県金庫(県の現金出納を扱う業務)を、1928年3月に総武銀行に移した。
1928年7月、総武銀行は三協と安房合同の2行を合併し、「千葉合同銀行」と改称した。同行の資本金480万円、預金量2,612万円(1928年12月末時点)はともに県下第一であり、営業範囲も東葛・木更津地域を除く県内全域に及んだ。
川崎銀行の目論見もあり、千葉合同銀行は発足直後から矢継ぎ早に合併や買収を行った。1928年から1931年にかけ、銚子、中山協和、片貝、滝沢(山武郡源村、現・東金市)、九十九里商業、佐原興業、松戸農商、千葉古川(安房郡北条町、現・館山市)、上総、佐貫の各行が同行に吸収された。1943年2月には、県東部で最後まで独立を維持していた東金銀行の営業を譲り受けた。まさに千葉県銀行界を席巻する勢いで、営業範囲は茨城県や神奈川県にまで広がった。
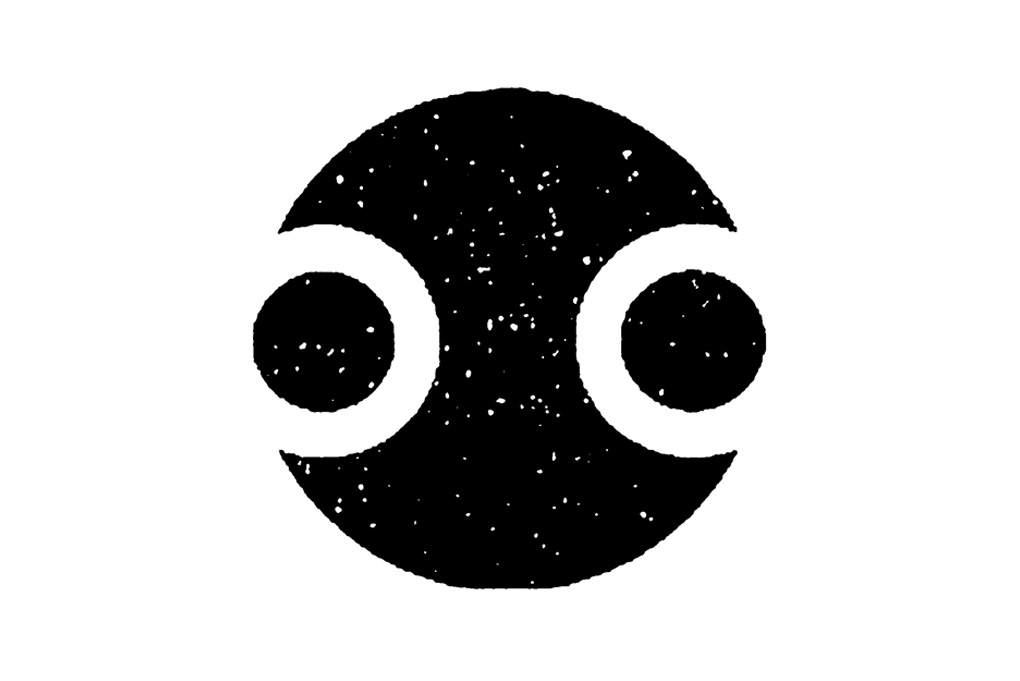
小見川農商銀行は1898年3月に資本金5万円で開業した。
開業間もなく、1900年末の蚕糸相場の暴落によって多数の業者が倒産し、横浜蚕糸銀行の破綻をきっかけに関東地方の銀行に取付けが広がったことで、小見川農商銀行も設立わずか3年で存亡の危機に直面した。
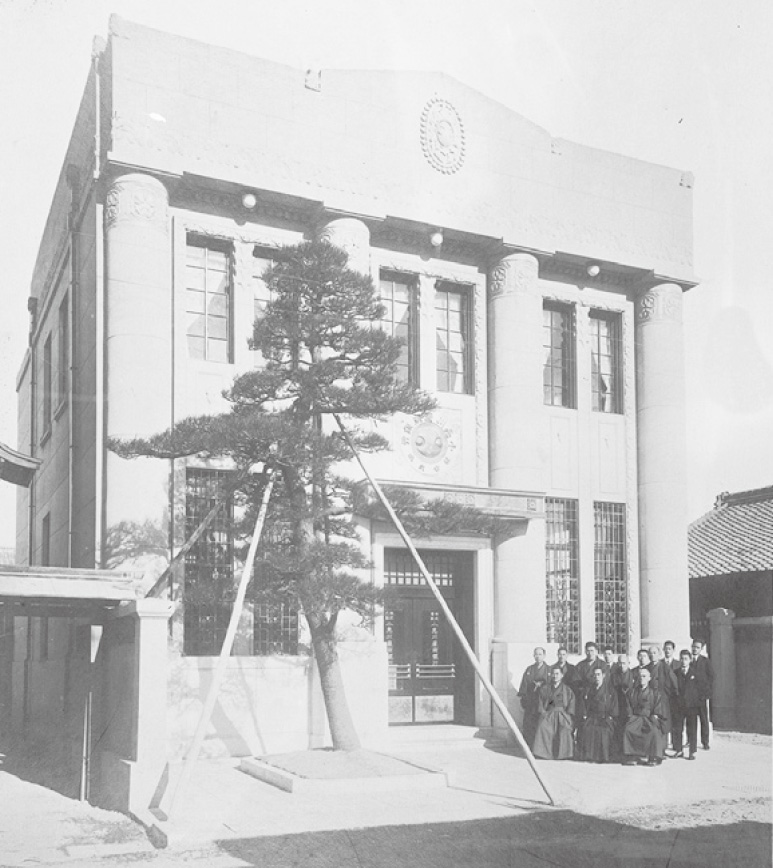
このときは重役の連帯責任として2万円を借り入れて苦境を切り抜け、1901年10月に績川(おみがわ)銀行(香取郡小見川町、現・香取市)を合併して資本金を20万円とし、配当率の引下げを行った。
短期間で経営の立て直しに成功した同行は、以後、簡素堅実を行風として経営を行った。
昭和期に入ると、政府や県は小見川農商銀行を県北東部の香取・海上・匝瑳の3郡における地域的合同の中心銀行に選定した。同行は周辺の銀行と協議を重ね、1928年9月に神崎銀行を合併した。このとき、神崎銀行の本店を神崎支店とし、職員もそのまま引き継いだ。
1941年頃から、小見川農商銀行にも県内銀行の大合同へ参加するよう呼びかけが行われた。自立経営に自信のあった同行は逡巡したものの、国策には抗えず、ついに新銀行設立に合流することとなった。
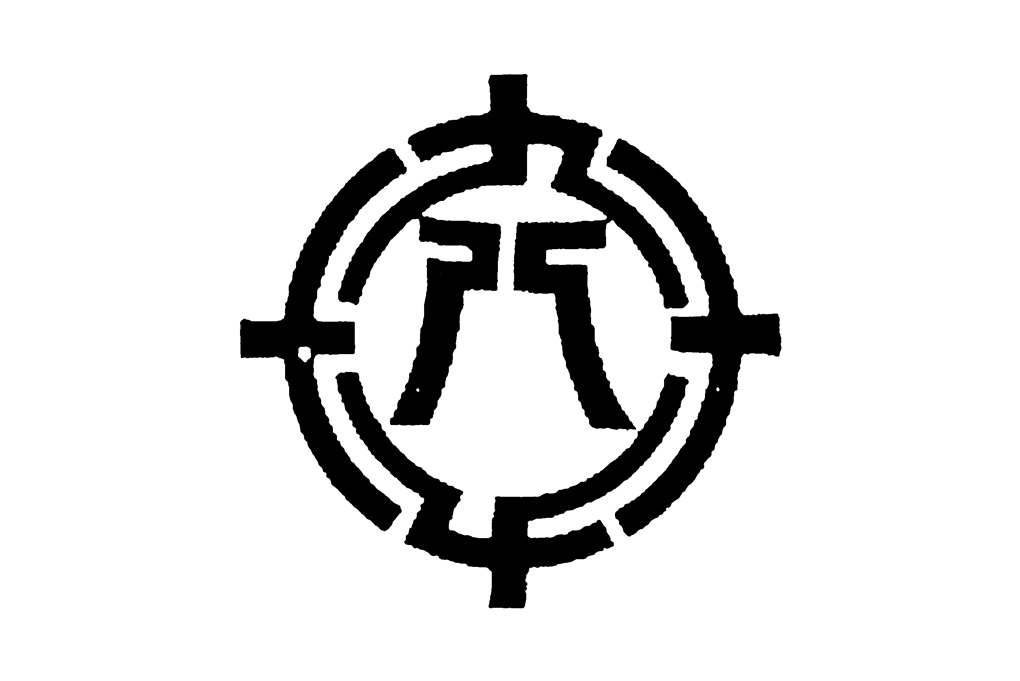
第九十八銀行の歴史は、士族と千葉町(現・千葉市)の地主などの有力者によって1878年に設立された第九十八国立銀行に始まる。資本金は12万円で、本店を千葉郡千葉町、出張所を市原鶴舞、安房八幡(現・館山市)、長狭横渚(現・鴨川市)に置いた。

同行は、1882年3月に安田銀行とコルレス契約を結び、同年4月には農商務省為換方安田善次郎の代理として、下総種畜場(のちの御料牧場)御用取扱いとなった。両行の関係はこのときに始まった。

その後、1883年の「国立銀行条例」改正により、1897年9月に普通銀行に転換し、株式会社第九十八銀行と改称した。
1901年の金融恐慌では、第九十八銀行も取付けに見舞われたが、大株主の安田銀行の支援でこの難局を切り抜けると、経営基盤の強化と店舗網の拡大に乗り出した。1907年7月に津田沼商業銀行、六軒商業銀行(印旛郡大杜村、現・印西市)の2行を買収して津田沼支店、六軒支店としたほか、横芝出張所を開設した。その後も大正期までに、八幡、成田、八日市場、船橋、木更津、北条(現・館山市)の各支店を相次いで開設した。
第1次世界大戦の戦中戦後の好況期には、政府の勧めに従って合併による規模拡大を推し進めた。1917年12月の一宮商業銀行を皮切りに、翌年11月に長南商業銀行、翌々年4月に花房銀行(安房郡鴨川町、現・鴨川市)を合併し、店舗数は20を数えた。
その後、第九十八銀行は1925年に本店を新築したのち、大多喜、幕張の2出張所を設けたにとどまり、合併も店舗増設も行わなかった。これは、監督会社であった安田保善社の方針と言われているが、前述の千葉合同銀行が合併による拡大路線を突き進んだのと対照的であった。
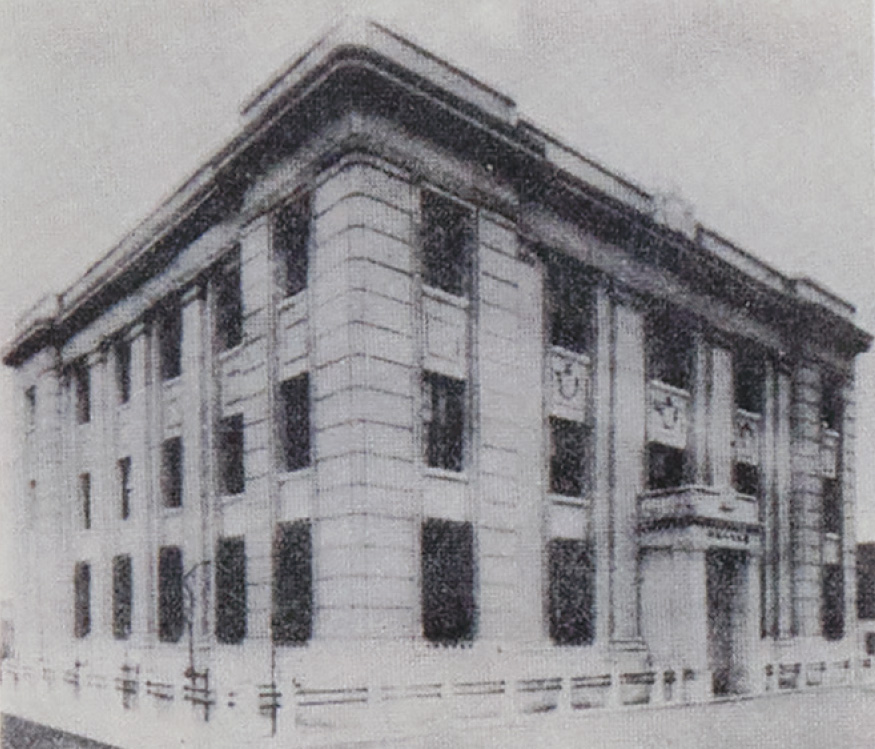
同行のこの方針は、結果的に弱体な中小銀行を取り込むことなく、経営の堅実さを示したが、緊迫化する戦時経済体制下の国策には従わざるを得ず、やむなく新銀行設立に合流することとなった。

貯蓄銀行は当初、普通銀行の小口資金吸収の機関として利用され、受け入れた預金は不健全な貸出に回されることが多く、しばしば取付けも発生した。このため、少額預金者を保護する目的で1921年に「貯蓄銀行法」が制定され、普通銀行による貯蓄銀行業務の兼営の禁止や法定最低資本金の引上げなどが定められた。これによって、貯蓄銀行の合併が進み、千葉県下でも同年に兼営銀行10行が千葉合同貯蓄銀行を設立して、各行の貯蓄部門を統合した。
一方、千葉貯蓄銀行は、千葉県農工銀行頭取らの発起により、1920年10月に資本金100万円で設立された。同行は設立間もない1922年2月、千葉合同貯蓄銀行を合併して資本金を200万円とし、県内唯一の貯蓄銀行となった。

その後、業績は順調に伸び、1930年には県の斡旋により山武銀行を買収したほか、当初は1店舗のみであった支店数も1933年には10にまで増えた。
しかし、戦時体制下に入ると、貯蓄銀行は資金運用の制限に加え、資金量が乏しいために軍需融資や統制機関向けの貸出に対応できなくなった。さらに、人手不足から集金制度の利点も生かせなくなり、経営難に陥る貯蓄銀行も増えてきた。1943年5月には、政府が普通銀行等の貯蓄銀行業務または信託業務の兼営を認めたことで、普通銀行の千葉銀行が同年8月から本支店で貯蓄預金業務(小口預金の受入れ)を取り扱うこととなり、合併気運がしだいに醸成されていった。
そうして、1944年3月に千葉貯蓄銀行は千葉銀行に合併された。
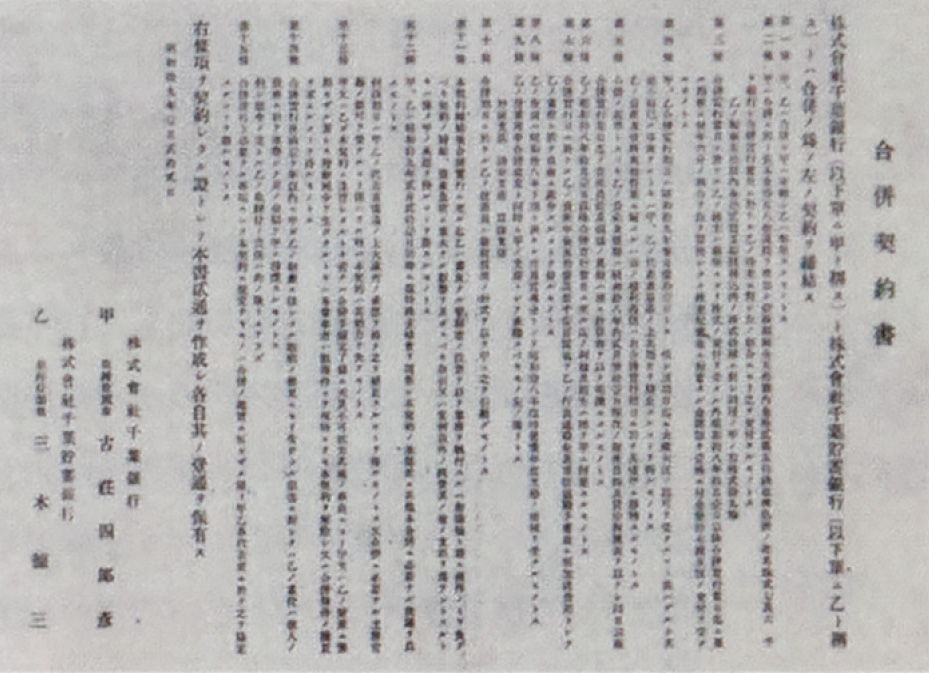
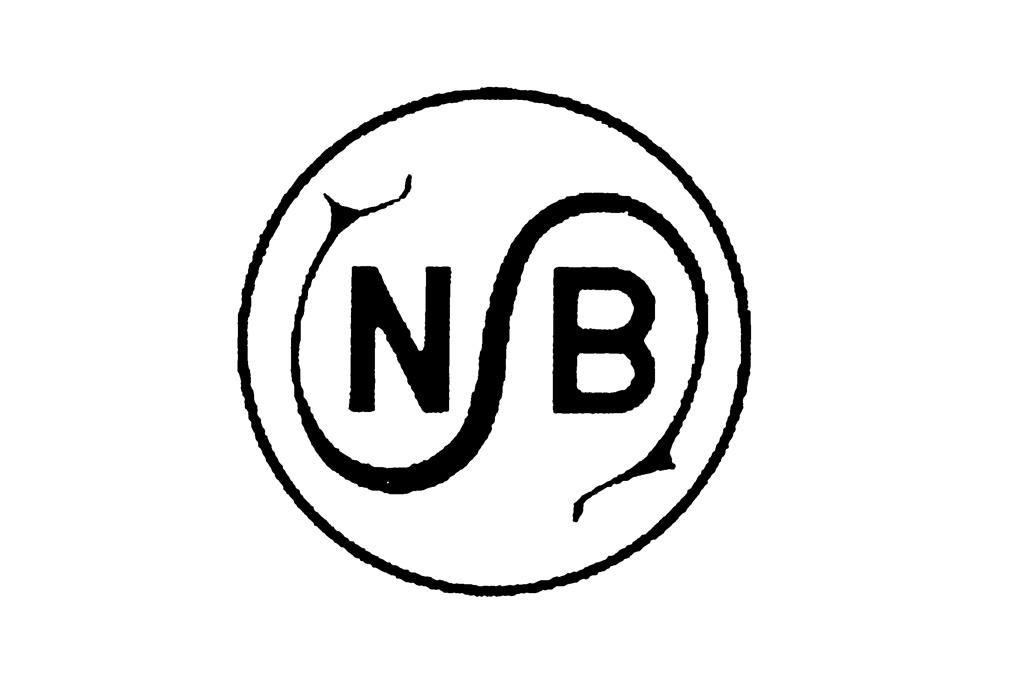
野田商誘銀行は、1900年5月に創立総会が開催され、資本金25万円で7月から営業を開始した。その後、1920年6月に増資によって資本金は100万円、1924年8月には300万円となった。また、同年12月に柏派出所を設置した。

当時、利用者の70%以上は醤油醸造家によって占められていた。1917年12月、野田醤油醸造組合の主要メンバーである茂木・高梨一族の個人企業を合同して野田醤油株式会社が設立されると、同行もその傍系企業の一つとして経営されるようになった。
同行の経営は堅実そのもので、利益の内部留保に力を注ぎ、設立後5年間は株式配当を行わなかった。重役は無報酬とすることも申し合わせた。
その後、一県一行主義の銀行合同が進められると、野田商誘銀行に対しても大蔵省銀行局から度々合併勧奨がなされた。野田醤油の傍系企業として特殊な経営体制にあったことで合同問題は難航したが、1944年に入り、四囲の情勢によってやむなく千葉銀行に営業を譲渡した。
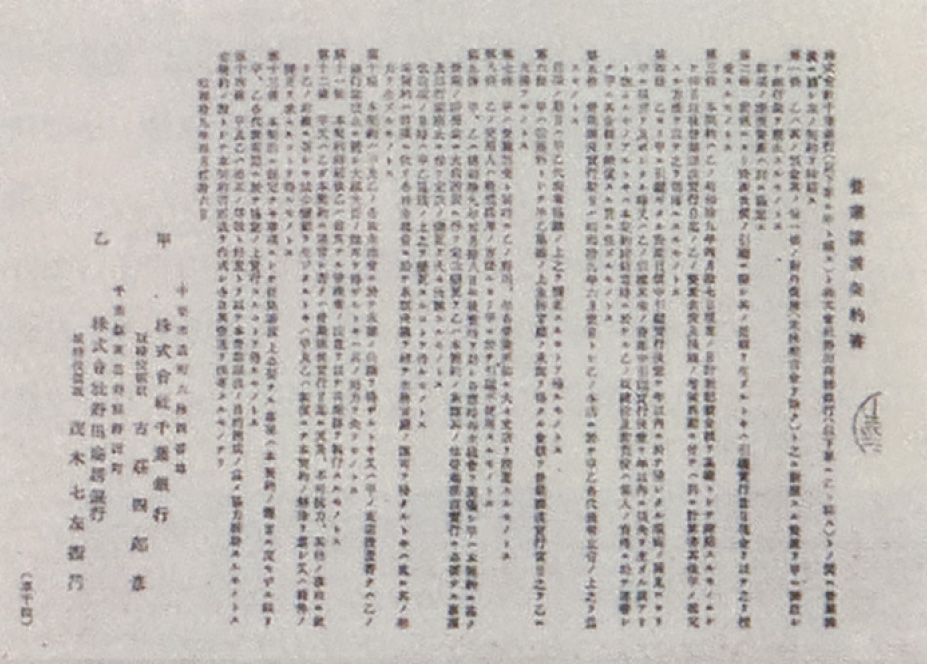
※7 金融恐慌
生糸輸出の不振などによる正貨流出を防ぐため、日本銀行が貸出の抑制・回収を図った結果、金利が著しく上昇し、金融逼迫を招いた。熊本第九銀行・熊本貯蓄銀行の支払停止を契機として、混乱が一斉に広がった。
※8 川崎銀行
水戸藩御用商人から東京に進出した川崎八右衛門が、1880年に東京市日本橋区檜物町(現・中央区日本橋3丁目)に設立した銀行。この川崎銀行を中核として、保険・信託など主として金融業に特化した東京川崎財閥を形成した。