目次
閉じる
- 第1部
- 第2部
- 第3部

目次
閉じる
1997年に明るみとなった大手金融機関による総会屋への利益供与などをきっかけに、企業に対して企業倫理が強く求められる時代へと変わっていった。当行は1997年8月、法令等遵守に係る全行横断的な組織として「企業倫理委員会」(現・コンプライアンス委員会)を設置するとともに、10月には総務部法務室をコンプライアンス担当部署に定めた。
翌年11月には「千葉銀行の企業倫理」を制定したほか、全職員に「コンプライアンスの手引」を配布してその徹底を図った。この手引書は「コンプライアンス・マニュアル」として改定を重ね、現在も活用されている。
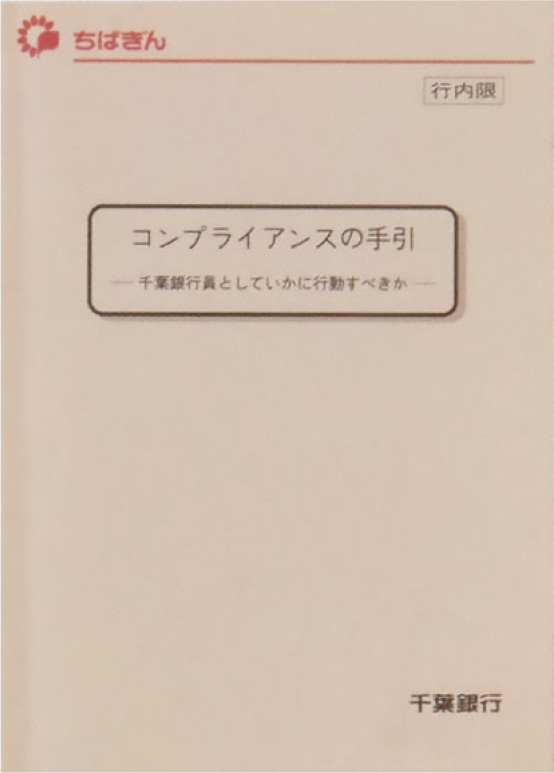
その後、1999年4月に金融監督庁が公表した「金融検査マニュアル」※21の最終案にも法令等遵守が盛り込まれたことで、銀行経営におけるコンプライアンスの重要性は一層高まっていった。
当行では、同年6月に監査部内にコンプライアンス統括室を設置し、コンプライアンスに係る基本規定となる「コンプライアンス規程」をはじめとして関連諸規定を整備していった(2001年6月に総務部に移設)。また、1999年度から毎年度「コンプライアンス・プログラム」を策定し、実効性のある施策に取り組んでいる。
この時期、バブル期の担保偏重主義や営業推進傾注の姿勢を見直し、信用リスク管理をいかに高度化していくかが金融機関共通の課題となっていた。高度化に向けた取組みは、1998年4月に導入された早期是正措置のもとで、適正な自己査定による償却・引当、信用リスク量の算定と貸出金利への反映、与信集中状況等のポートフォリオ分析というかたちで具体化していった。
当行では、1993年12月に融資第一部内に融資企画室を設置して信用リスク管理体制の再構築に着手した。不動産担保の明確な評価基準を設けるとともに、翌年5月には評価業務を関連会社のちばぎん保証に委託することで、評価の標準化と厳正化を図った。1996年4月には融資第一部を審査部、融資第二部を管理部と改称して両部の役割を明確にするとともに、「融資審査の基本方針」を明文化した。
1999年には統合リスク管理体制へと移行し、「信用リスク管理委員会」を設置して、与信ポートフォリオの状況などのモニタリングに経営陣が関与するようにした。さらに、2002年10月には「グループ別与信上限管理制度」を導入し、融資先グループの格付けに基づく合算与信上限額を定めるとともに、これを超過する場合の融資対応方針については経営会議で定期的に協議する体制とした。
リスク管理の重要性が高まるなか、当行は1994年12月、経理部内に地方銀行で初めてリスク管理室を設置した(1997年10月に経営企画部に移設)。同室は、マーケット取引におけるロスカットルール※22やクレジットライン(与信限度額)の適用状況の監視や取引内容のチェックをマーケット部門から独立して行うミドルオフィス(管理部署)であった。さらに、1995年4月にはALM委員会の委員長を総合企画部担当役員から頭取に変更し、マーケットリスクに対する経営の関与を強めた。
こうしたミドルオフィスによるマーケット取引でのリスク管理の厳正化と、1998年3月期より適用されたBIS基準のマーケットリスク規制※23に対応するため、1998年3月にリスク管理システムを稼働した。
1999年6月にはリスク管理室の機能を拡充して、名称を統合リスク管理室に改めた。同室がマーケットリスクだけでなく、多様なリスクを統合管理していくとともに、個別の信用リスクは審査部、事務リスクは事務企画部、システムリスクはシステム部など、各リスクの管理部署を明確にした。
また、この時期には金融検査マニュアルで示されたリスク管理体制のチェック項目をもとに、関連規定の整備も進めた。1999年10月、「リスク管理の基本方針」「信用リスク管理規定」「市場関連リスク管理規定」「流動性リスク管理規定」「事務リスク管理規定」「システムリスク管理規定」などの制定をもって、組織・規定の両面で統合リスク管理体制への移行が完了した。
当行では、リスクとコストを反映した部門別・営業店別・取引先別の収益管理を行うため、2002年4月に収益管理システムを導入した。
そして、資金粗利益算出にスプレッドバンキング、経費算出に活動基準原価計算(ABC:Activity Based Costing)方式、信用コスト算出にみなし引当制度を採用し、リスク調整後収益率(RAROA:Risk Adjusted Return On Assets)等による管理の浸透を図った。さらに、2003年下期より本格的に部門別リスク資本配賦を導入し、資本コスト控除後純益(RACC:Return After Capital Cost)による部門別収益管理を開始した。なお、2010年12月に収益管理システムを更改し、算出データの拡充等を行った。
また、財務会計においては、公正で透明なルール整備の一環として新たな会計制度が順次導入されていった。連結財務諸表中心の開示への移行、税効果会計の導入(ともに1999年3月期)、金融商品に関する時価会計の導入(2001年3月期)、四半期決算開示(2006年3月期)などがその例で、当行もこれら新ルールに対応した。
21世紀を迎えるにあたり、世界的に注目されたのが、「コンピュータ西暦2000年問題」※24であった。当行では、頭取を委員長とする「コンピュータ西暦2000年問題対策委員会」を設置して、すべてのシステム・機器類のテスト・プログラム修正や、危機管理計画の策定・訓練などに万全を期した結果、特段の問題なく終息した。
※21 金融検査マニュアル
正式名称は「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」。金融当局の検査官が金融機関を検査する際に用いる手引書。1999年7月に制定され、更新を重ねつつも2019年12月に廃止された。
※22 ロスカットルール
マーケット取引において一定水準以上の損失が出た場合に、保有ポジションを強制的に決済する取決め。
※23 BIS基準のマーケットリスク規制
信用リスクアセットにマーケットリスクを加えて分母としたうえで、自己資本比率8%以上を求めるもの。
※24 コンピュータ西暦2000年問題
コンピュータが2000年を表す「00」年を、1900年と認識してしまうことにより、誤作動や停止が起こる可能性のこと。