目次
閉じる
- 第1部
- 第2部
- 第3部

目次
閉じる
バブル崩壊による不良債権問題など経営環境が厳しさを増すなかで、当行は玉置頭取のもと、1993年4月に「経営方針96」(~1996年3月)を打ち出した。「トップバンクとしての責務の完遂」という副題がつけられたこの方針は、地域発展のための諸活動を通じて営業基盤の拡充と経営体質の強靭化を進めるというものであった。「もっともっとお客さまのために」をスローガンに、顧客応対向上を図る「マイカスタマー・マイブランチ運動」を展開した。
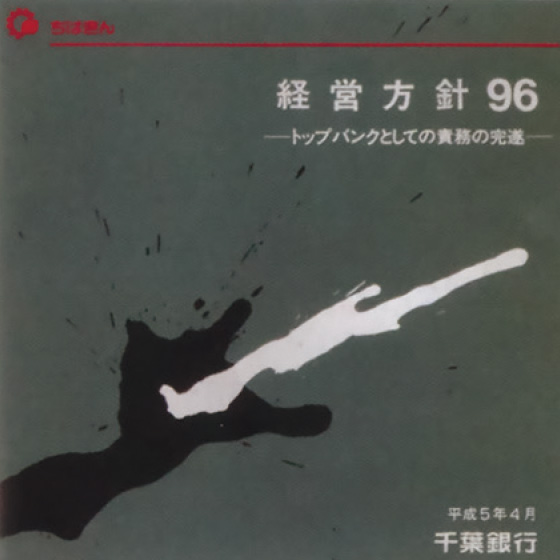
続く1996年4月、「経営方針2001」(~2001年3月)を策定した。この方針では、経営環境の変化を前向きにとらえ、21世紀に向けたさらなる飛躍のため、営業基盤の一層の拡充とより強固な経営体質の構築に挑戦するとした。また、不良債権の解消と発生防止に万全を期すとともに、激化する金融競争を勝ち抜くため、経営課題に①総合金融サービスの強化・推進、②取引シェアの一層の拡大、③強固な安定収益体質の構築、④活力あふれる人材の育成を掲げた。

1997年6月、玉置頭取が取締役会長に、副頭取の早川恒雄(はやかわ つねお)が第6代頭取に就任した。当行の頭取は4代続けて日本銀行出身者であったため、生え抜きの頭取誕生は39年ぶりであった。なお、早川頭取は千葉県経済同友会代表幹事(1998年7月~2007年8月)などの公職を務めた。
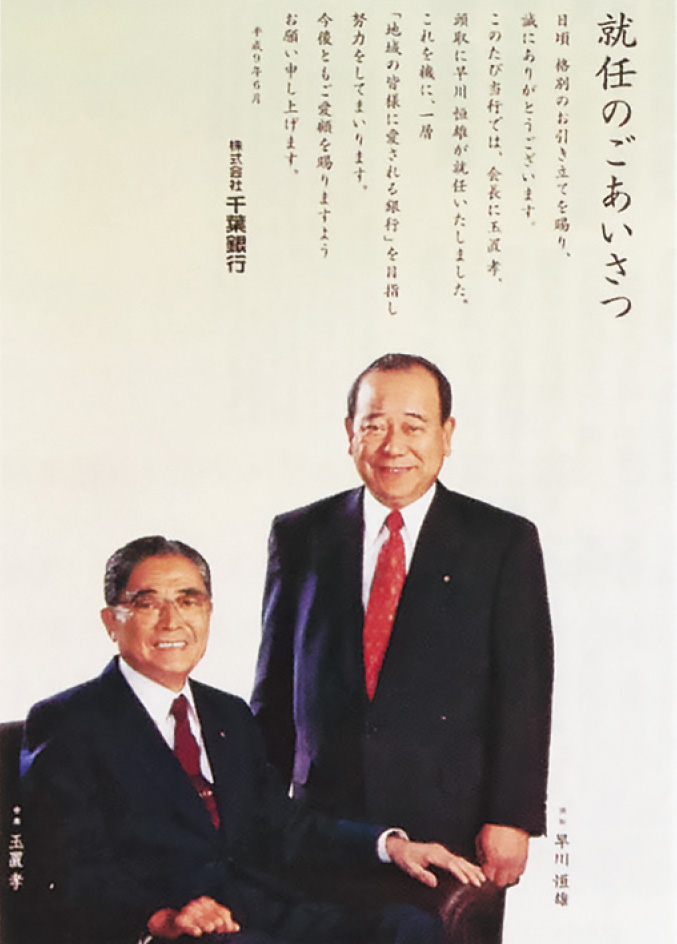
早川頭取のもと、「経営方針2001」の期限を待たず、1999年10月に第6次中期経営計画「A・C・T2003」(~2003年3月)がスタートした。本中計では、目指すべき銀行像を「最も質の高い『地域の総合金融サービスグループ』」とし、主要課題に①強固な財務基盤の早期確立、②顧客基盤の強化・拡大、③経営システムの革新を掲げた。また、業務純益、自己資本比率、OHRなどの具体的な数値目標も示した。なお、計画名称の「A・C・T」は、Aggressive、Creative、Toughの頭文字をとったもので、「積極的かつ創造的に、粘り強く行動する」という心構えを示した。
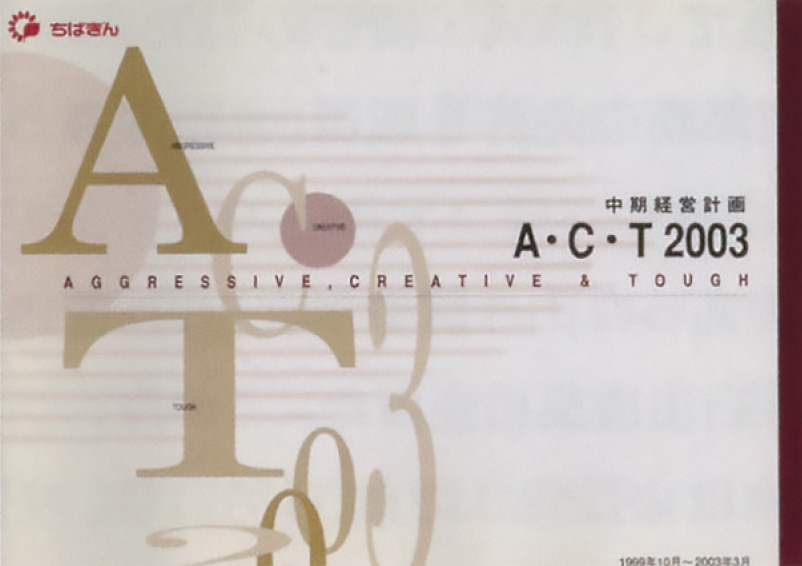
続いて2003年4月には、第7次中期経営計画「創造とスピードの100週間」(~2005年3月)がスタートした。本中計の特徴はスピード重視にあり、2年間の計画期間を「100週間」ととらえて、週単位で主要課題に取り組んでいくものであった。目指すべき姿(銀行像)は前中計と変更せず、主要課題を①持続的な収益力強化(収益構造の変革、経費の削減)、②経営システムの変革(収益構造変革のための営業体制構築、収益管理体制の一新、ガバナンス体制の再構築、新人事制度の定着化等による活力ある組織への変革、高度なリスク管理体制・コンプライアンス体制の構築、お客さま満足度の更なる向上)とした。
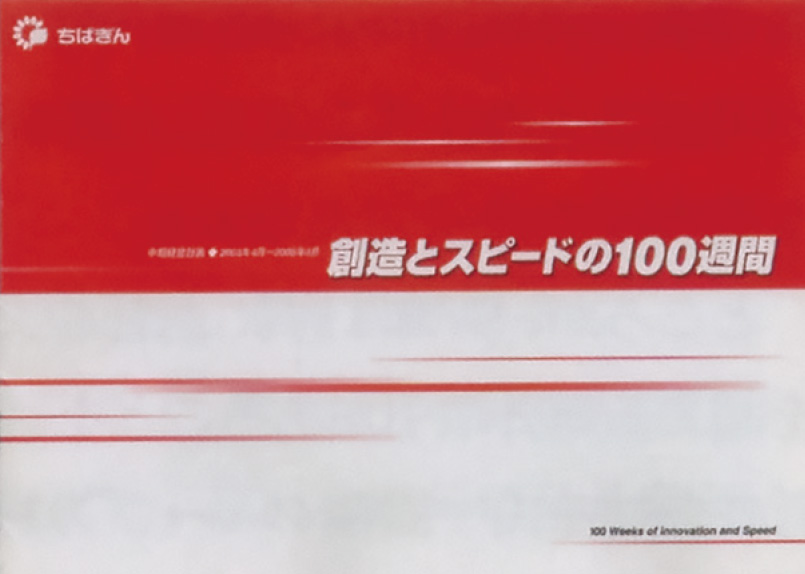
早川頭取は就任当初からCS(Customer Satisfaction:顧客満足度)の向上に注力した。頭取を委員長とする「CS向上委員会」において、1998年10月より全行を挙げて取り組む「ベストプラクティス’99」をスタートさせた。この活動で定めた企業行動指針「顧客満足(CS)・従業員満足(ES)、社会満足(SS)の向上」と、職員行動指針「お客さまに感謝をしよう、お客さまの期待に応えよう、お客さまに感動を与えよう」はのちのCSR※8活動へとつながっていった。
また、CS向上活動を主要営業施策の一つとし、1999年6月に新設した営業統括部支店統括グループをCSの統括部署に定めるなど、行内での定着を図っていった。
こうした活動が実を結び、1999年12月に実施された日本経済新聞社の「第6回銀行支店サービス調査」において、当行は総合得点トップの評価を得た。
山一證券の自主廃業に伴い、1998年3月、系列の中央証券(現・ちばぎん証券)がグループ入りした。山一證券グループに代わって当行に安定株主としての株式取得と業務提携の申し入れがあったもので、当行グループで株式の48%を取得し、同社を関連会社とした。当時、当行は証券関連業務の拡充が急務であり、県内に10店舗を有する同社とは銀証連携の相乗効果が期待できると考えた。
中央証券の歴史は古く、前身の一つである小布施証券は1883年に東京で創業し、戦前は業界一の出来高を上げるほどの名門で、東京証券取引所最古の正会員でもあった。

もう一つの鳥海証券は1923年に千葉県長生郡茂原町(現・茂原市)で創業し、地域密着の営業を続けていた。
2社は不良資産処理などの問題からそれぞれ山一證券の傘下に入った後、1981年10月に対等合併し、中央証券が発足した。
※8 CSR
Corporate Social Responsibilityの略で、企業の社会的責任を指す。顧客、株主、従業員などすべてのステークホルダーの満足を実現し、ともに持続的に発展していくことを目的とする。